増田彰久、大田省一『建築のハノイ』
出版情報
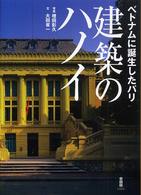
| 副題 | ベトナムに誕生したパリ |
|---|---|
| 写真 | 増田彰久 |
| 文 | 大田省一 |
| 出版社 | 白揚社 |
| 出版年 | 2006 |
| ISBN | 978-4-8269-0127-7 |
| 価格 | ¥2800(2006年) |
内容
ハノイに散在する植民地期の建築を、写真と解説文で一般向けに紹介している。写真は一部モノクロ。ハノイに限り、掲載された建築の地図が「ハノイ建築ガイドマップ」として掲載されている。
解説部では、気候に適応するための工夫、建築物の起工に至るまでの経緯や様式の変遷、その背後にあるヨーロッパの芸術運動、植民地をめぐる政治情勢を簡潔に記述している。
また、植民地建築に影響を及ぼしたヴェトナムの伝統的な建築や、南部・中部の建築物についても、一章ずつ割いている。
コメント
鮮明で美しい写真に魅入られる一冊ですが、建物を包む喧噪もまたハノイの醍醐味だと思います。これを手に、ハノイへどうぞ。
ハノイの官公庁にどうして黄色の建物が多いのか、という長年の個人的な謎を本書はスッキリ解いてくれました。
更新履歴
2010/06/14 新規
新規作成。
桃木至朗(編)『海域アジア史研究入門』
出版情報
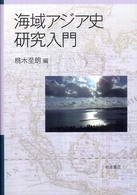
| 編集 | 桃木至朗 |
|---|---|
| 編集委員 | 桃木至朗、山内晋次、藤田加代子、蓮田隆志 |
| 出版社 | 岩波書店 |
| 出版年 | 2008 |
| ISBN | 978-4-00-022484-0 |
| 価格 | ¥2800(2008年) |
内容
海のアジアについて、史学雑誌の「回顧と展望」を質量共にもっと深いレベルに落とし込んだタイプの概説書。
時系列に著者を割り振り、そこで割り振れなかったテーマについては個別に章を割いている構成で、著者らは主立ったテーマに沿って代表的な資料や業績を紹介つつ、解明と未解明のテーマを整理し、2008年時点でいかなる展望が描けるかを提示している。
目次
- 総説[桃木至朗/山内晋次/藤田加代子/蓮田隆志]
- 第1篇 通時的パースペクティブ
- 第I部 中世〈9 世紀―14 世紀前半〉
- 第1章 中国人の海上進出と海上帝国としての中国[榎本渉]
- 第2章 モンゴル帝国と海域アジア[四日市康博]
- 第3章 宋元代の海域東南アジア[深見純生]
- 第4章 日本列島と海域世界[山内晋次]
- 近世前期〈14世紀後半―17世紀初頭〉
- 第5章 明朝の国際システムと海域世界[岡本弘道]
- 第6章 琉球王国の形成と展開[上里隆史]
- 第7章 日明の外交と貿易[伊藤幸司]
- 第8章 日朝多元関係の展開[関周一]
- 第9章 倭寇論のゆくえ[橋本雄/米谷均]
- 第10章 「交易の時代」の東・東南アジア[中島楽章、桃木至朗]
- 第11章 ヨーロッパ勢力の台頭と日本人のアジア進出[岡美穂子]
- 近世後期〈17世紀中葉―19世紀初頭〉
- 第12章 経済史から見た近世後期の海域アジア[藤田加代子]
- 第13章 近世後期東アジアの通交管理と国際秩序[渡辺美季/杉山清彦]
- 第14章 蝦夷地と琉球 ―― 近世日本の2つの口[谷本晃久/深澤秋人]
- 第15章 東南アジアの「プロト国民国家」形成[蓮田隆志]
- 第16章 18世紀の東南アジアと世界経済[太田淳]
- 第17章 近世から近代へ ―― 近世後期の世界システム[秋田茂]
- 第I部 中世〈9 世紀―14 世紀前半〉
- 第2篇 各論
- 第18章 海陸の互市貿易と国家 ―― 宋元時代を中心として[佐藤貴保/向正樹]
- 第19章 港市社会論 ―― 長崎と広州[川口洋平/村尾進]
- 第20章 貿易陶磁[坂井隆]
- 第21章 海産物交易 ―― 「竜涎香」をめぐって[真栄平房昭]
- 第22章 造船技術 ―― 列島の木造船,終焉期のけしき[出口晶子]
- 第23章 航海神 ―― 媽祖を中心とする東北アジアの神々[藤田明良]
- 第24章 漂流,漂流記,海難[劉序楓]
- 第25章 海域アジア史のための東アジア文献史料[渡辺佳成/飯岡直子]
- 和・中・韓文 文献目録
- 欧文 文献目録
- 編者あとがき
- 執筆者一覧
コメント
海に関係するテーマに興味のある人は必読。
簡単に内容を紹介していますが、執筆にものすごく手間暇がかかるタイプの本だと思います。
目次もCSSでコントロールし辛いタイプで、割り切ってタグ付けしました。
更新履歴
2008/05/31 新規
新規作成しました。
北川香子『カンボジア史再考』
出版情報

| 著者 | 北川香子 |
|---|---|
| 出版社 | 連合出版 |
| 出版年 | 2006 |
| ISBN | 4-89772-210-1 |
| 価格 | ¥2500(2006年) |
内容
主な著述対象はポスト・アンコール期のカンボジアであるが、カンボジア史全体を捉え直すことを目的としている著作。問題点の提示、カンボジア史の地理的範囲設定から書き起こし、カンボジア史の主なトピックについて過去の史学史の状況などを解説した前半部分と、専門であるポスト・アンコール史の概要説明を行う後半部分に分かれた構成となっている。
セデスに代表される植民地史学が未だ残るカンボジア史で、状況整理と問題点の抽出を通して、その軛から脱却しようとする試み。
コメント
高校時代の授業で、カンボジアがいきなり現代史に再出現した時の違和感があったのですが、それを歴史学の問題として提示してくれた本です。
更新履歴
2008/03/20 新規
新規登録しました。
笹川秀夫『アンコールの近代』
出版情報
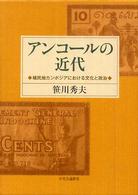
| 副題 | 植民地カンボジアにおける文化と政治 |
|---|---|
| 著者 | 笹川秀夫 |
| 出版社 | 中央公論新社 |
| 出版年 | 2006 |
| ISBN | 4-12-003746-0 |
| 価格 | ¥7000(2006年) |
内容
植民地期以後のカンボジアの文化芸能、政治、歴史教育、ナショナリズム等の観点から網羅的にアンコール遺跡の受容史、ひいてはアンコール遺跡の政治性を叙述した著作。著者の博士論文に加筆・修正を行ったもの。
植民地時代のフランス東洋学の影響はもちろん、周囲の国家(特に、アンコール遺跡を領有していた過去を持つタイ)との関わりも重視している。
コメント
2006年はカンボジア、タイの近現代史についての著作が豊作でした。本書はその1冊。
更新履歴
2008/03/02 新規
新規作成しました。
Woodside, A. B. “Vietnam and the Chinese Model”
出版情報
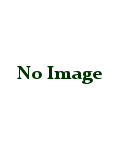
| 副題 | A Comparative Study of Vietnamese and Chinese Government in the First Half of the Nineteenth Century |
|---|---|
| 著者 | Alexander Barton Woodside |
| 発行 | Harvard University Press |
| 出版年 | 1988 |
| ISBN | 0-674-93721-X |
内容
19世紀前半のヴェトナム政府と中国政府との比較を行った研究。ただし、その比較の範囲は多岐にわたり、文学、官僚組織、中央政府と地方、対外関係に言及している。
コメント
入院中に読みましたが、理解できたとは言い難い状態です‥‥。
更新履歴
2008/01/05 更新
アフィリエイト対応。
2007/11/19 更新
新規作成。
坪井善明『近代ヴェトナム政治社会史』
出版情報

| 副題 | 阮朝嗣徳帝統治下のヴェトナム 1847‐1883 |
|---|---|
| 著者 | 坪井善明 |
| 出版社 | 東京大学出版会 |
| 出版年 | 1991 |
| ISBN | 4-13-036057-4 |
| 価格 | ¥6600(1991年) |
内容
ヴェトナムの植民地化を、本来支持層であったはずの文紳階層と阮朝嗣徳帝との決裂を背景として描いている。
国内の社会・経済情勢と国際関係を絡めたオーソドックスな構成である。刊行当時ほとんど用いられなかった史料を使用している点と、この時期に関してヴェトナムそのものを基点とした(特に書籍の形での)先行業績が少なかったという点で非常に有用である。
コメント
すらすら読めます。ヴェトナムの植民地化について、いまいち経緯がよく解らない人はこの本から始めると良いかもしれません。私ももやもやした部分がこの本で随分すっきりしました。中国南部の海賊や、太平天国系の武装集団=黒旗軍・黄旗軍・白旗軍について知りたい人もこの本は一読の価値があるでしょう。
ヴェトナムの村落居住者(農民ら)に関する記述があまり無いので、そのあたりが個人的な不満です。
更新履歴
2008/01/05 更新
アフィリエイト対応。
2007/04/29 更新
リニューアルに伴い、データをコンバートしました。
阮福暎(1762‐1820)
人物情報
| 姓名 | 阮福暎 |
|---|---|
| Quốc ngữ | Nguyễn Phúc Ánh |
| 主な日本語読み | グェン・フック・アィン |
| 別名 | 阮福映(一般的な表記) |
帝号など
| 帝号 | 嘉隆帝 |
|---|---|
| Quốc ngữ | Gia Long Đế |
| 主な日本語読み | ザロンてい |
| 在位年 | 1802‐1820 |
| 廟号 | 世祖 |
事績
ヴェトナム阮朝の創始者。
1600年代から1800年代にかけてヴェトナム中・南部に広南(Quảng Nam、クァンナム)国を築いていた阮(Nguyễn、グェン)氏の一族出身。広南国定王阮福淳の甥であり、西山(Tây Sơn、タイソン)阮氏の攻撃により広南国阮氏が滅亡した後の生き残りである。
広南国滅亡後、1780年に嘉定(Gia Định、ザーディン、現ホーチミン)にて即位。その後、西山阮氏に敗れてカンボジアやタイに亡命する。ここでラーマ1世や反西山の姿勢をとる華僑の援助を取り付け、西山阮氏との激しい戦いを繰り広げつつ、南部ヴェトナムを中心に勢力を広げる。1788年に嘉定城を陥落させた。
翌年、幼い長子阮景(Nguyễn Cảnh、グェン・カィン)を名代としてフランスのルイ16世との間にヴェルサイユ同盟条約を結ぶも、結局フランス国家としての援助は得られず、アドラン司教ピニョーがフランス人志願兵をかき集めた。
1801年にはフエを陥落させ、翌1802年、ハノイを奪還して西山阮氏を滅ぼし、南北ヴェトナムを統一する。
1804年、清より“越南國王”として冊封された。
彼自身は当初“農耐(Nông Nại、ノンナイ)”の国号を使用しており、冊封時には“南越”の国号を希望していたが、前漢を圧迫して両広まで版図におさめた南越の号を使用することに清が難色を示し、妥協して南越をひっくり返した“越南”を使用することとなった。これは“越南”も“南越”もヴェトナム語の文法では“南越”となるためである。
南北統一後、均田制と『皇越律令』を発布したが、嘉隆帝は南部・北部を直接支配することは避け、総鎮を置いて間接的な支配を行った。
参考文献
- 石井米雄(監修)、『ベトナムの事典』、同朋舎、1999、P154l他
コメント
苛烈きわまる戦争を20年以上経験してドラマチックな人生にもかかわらず、いまいち地味な印象の人物。彼の廟は夫婦並んだ珍しい作りだそうです。
更新履歴
2007/04/03 新規作成
リニューアルに伴い、データをコンバートしました。
古田元夫『ベトナムの世界史』
出版情報

| 副題 | 中華世界から東南アジア世界へ |
|---|---|
| 著者 | 古田元夫 |
| 出版社 | 東京大学出版会 |
| 出版年 | 1995 |
| ISBN | 4-13-023045-X |
| 価格 | ¥2678(1996年) |
内容
自国を南の中華「南国」と捉え、中国「北国」と対等化・相対化してきたのが近代以前のヴェトナムだった。これが植民地化、独立運動、ベトナム戦争という時間の流れの中で、華夷秩序という世界認識から離れ、「東南アジア世界」の構成員であるという位置づけを行うまでの過程を論じている。そういう意味で「ベトナムの・世界史」ではなくて「ベトナムの世界・史」の意味合いが濃い。
コメント
(東京大学の)大学1-2年生向けに書かれた講義のテキストなので読もうと思えば一気読みできます。
これを読んだときの衝撃は大きく、読んだ後、実際に眩暈を起こしたのを覚えています。近現代史はこういう研究をするのだと刷り込まれました。
更新履歴
2008/01/05 更新
アフィリエイト対応。
2007/04/02 更新
リニューアルに伴い、データをコンバートしました。