増田彰久、大田省一『建築のハノイ』
出版情報
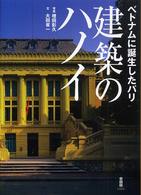
| 副題 | ベトナムに誕生したパリ |
|---|---|
| 写真 | 増田彰久 |
| 文 | 大田省一 |
| 出版社 | 白揚社 |
| 出版年 | 2006 |
| ISBN | 978-4-8269-0127-7 |
| 価格 | ¥2800(2006年) |
内容
ハノイに散在する植民地期の建築を、写真と解説文で一般向けに紹介している。写真は一部モノクロ。ハノイに限り、掲載された建築の地図が「ハノイ建築ガイドマップ」として掲載されている。
解説部では、気候に適応するための工夫、建築物の起工に至るまでの経緯や様式の変遷、その背後にあるヨーロッパの芸術運動、植民地をめぐる政治情勢を簡潔に記述している。
また、植民地建築に影響を及ぼしたヴェトナムの伝統的な建築や、南部・中部の建築物についても、一章ずつ割いている。
コメント
鮮明で美しい写真に魅入られる一冊ですが、建物を包む喧噪もまたハノイの醍醐味だと思います。これを手に、ハノイへどうぞ。
ハノイの官公庁にどうして黄色の建物が多いのか、という長年の個人的な謎を本書はスッキリ解いてくれました。
更新履歴
2010/06/14 新規
新規作成。
伊藤正子『民族という政治』
出版情報

| 副題 | ベトナム民族分類の歴史と現在 |
|---|---|
| 著者 | 伊藤正子 |
| 出版社 | 三元社 |
| 出版年 | 2008 |
| ISBN | 978-4-88303-234-1 |
| 価格 | ¥3800(2008年) |
内容
1960年代よりはじまったベトナムの民族確定作業の経緯、ドイモイ後に始まった民族確定見直し作業とその顛末を、各種の資料と先行研究、及びフィールド調査をもって描く。
国家によって決められた公定民族(本書では「国定民族」)という枠組みをめぐる、国家、地方行政府、当人達の政治的な関係性に注目し、上から民族を規定することの限界を明らかにしている。
目次
- 序論
- 第1節 本書の目的
- 第2節 本書の構成
- 第3節 研究手法
- 第4節 先行研究
- 第5節 ベトナム少数民族外観
- 第1章 ベトナム民主共和国における民族確定作業
- 第1節 ベトナム民族学の誕生
- 第2節 中国の民族識別作業
- 第3節 ベトナム民主共和国における民族確定作業
- 第2章 ドイモイ下の少数民族援助・優遇政策
- 第1節 1989年の共産党政治局22号決議とその背景
- 第2節 「135プログラム」の目的と対象
- 第3節 「135プログラム」の結果
- 第4節 「135プログラム」の課題
- 第5節 「135プログラム」第2フェーズ
- 第3章 21世紀の民族確定見直し作業
- 第1節 1999年の国勢調査とサブグループからの不満の噴出
- 第2節 声をあげたサブグループ ①カオランとサンチー
- 第3節 声をあげたサブグループ ②グオン
- 第4節 総括セミナーと国定民族成分リストの行方
- 第5節 声が届かないサブグループ
- 第4章 利用される「極少少数民族」オドゥ族
- 第1節 オドゥ族の居住状況
- 第2節 来歴をめぐる伝説
- 第3節 創られた「自称」
- 第4節 民族混淆状況と言語
- 第5節 オドゥ族の分類の歴史 ― “絶滅”の危機? ―
- 第6節 激増する「オドゥ族」
- 第7節 降ってわいたダム建設
- 第8節 民族別「優先」移住と家族の離散 ― 本当の危機 ―
- 第9節 オドゥ族への特別のプログラムとトゥオンズオン県の思惑
- 第10節 移住先でのオドゥ族と新たな民族間対立
- 結論 権益としての民族 ― 国家・地方政府・当人たち
- 資料
- 参考文献・インタビュー一覧
- あとがき
- 人名・事項索引
コメント
装丁と帯のコピー(「ある『民族』とされることが、人々になにをもたらし、なにを求めさせるのか」)がよくできており、本の内容をよく表しています。
公式ではない自称の民族名が現場レベルでは黙認されているというベトナムのやり方が不満のガス抜きになっている、という指摘が目を引きます。
また、ベトナムに「キン族の単一性」という大前提があることを、はっきりと(疑義をもって)示したのも面白い視点。
更新履歴
2010/04/18 新規
新規作成しました。
笹川秀夫『アンコールの近代』
出版情報
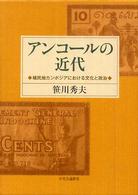
| 副題 | 植民地カンボジアにおける文化と政治 |
|---|---|
| 著者 | 笹川秀夫 |
| 出版社 | 中央公論新社 |
| 出版年 | 2006 |
| ISBN | 4-12-003746-0 |
| 価格 | ¥7000(2006年) |
内容
植民地期以後のカンボジアの文化芸能、政治、歴史教育、ナショナリズム等の観点から網羅的にアンコール遺跡の受容史、ひいてはアンコール遺跡の政治性を叙述した著作。著者の博士論文に加筆・修正を行ったもの。
植民地時代のフランス東洋学の影響はもちろん、周囲の国家(特に、アンコール遺跡を領有していた過去を持つタイ)との関わりも重視している。
コメント
2006年はカンボジア、タイの近現代史についての著作が豊作でした。本書はその1冊。
更新履歴
2008/03/02 新規
新規作成しました。
古田元夫『ベトナムの世界史』
出版情報

| 副題 | 中華世界から東南アジア世界へ |
|---|---|
| 著者 | 古田元夫 |
| 出版社 | 東京大学出版会 |
| 出版年 | 1995 |
| ISBN | 4-13-023045-X |
| 価格 | ¥2678(1996年) |
内容
自国を南の中華「南国」と捉え、中国「北国」と対等化・相対化してきたのが近代以前のヴェトナムだった。これが植民地化、独立運動、ベトナム戦争という時間の流れの中で、華夷秩序という世界認識から離れ、「東南アジア世界」の構成員であるという位置づけを行うまでの過程を論じている。そういう意味で「ベトナムの・世界史」ではなくて「ベトナムの世界・史」の意味合いが濃い。
コメント
(東京大学の)大学1-2年生向けに書かれた講義のテキストなので読もうと思えば一気読みできます。
これを読んだときの衝撃は大きく、読んだ後、実際に眩暈を起こしたのを覚えています。近現代史はこういう研究をするのだと刷り込まれました。
更新履歴
2008/01/05 更新
アフィリエイト対応。
2007/04/02 更新
リニューアルに伴い、データをコンバートしました。